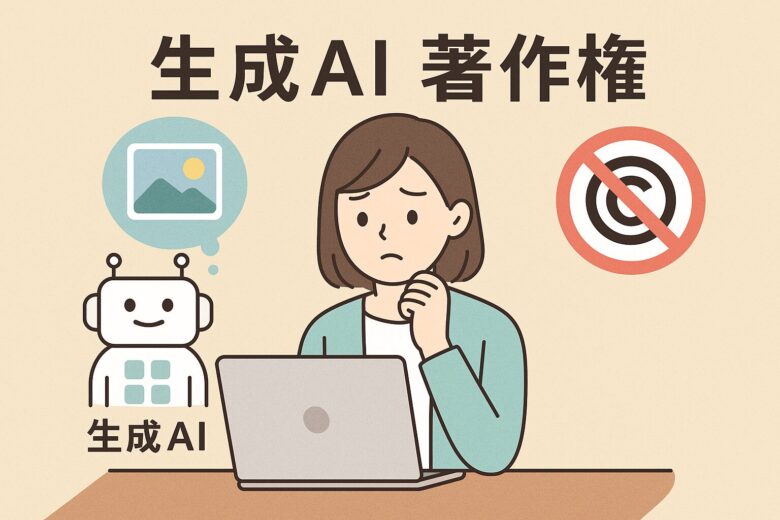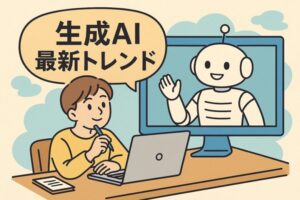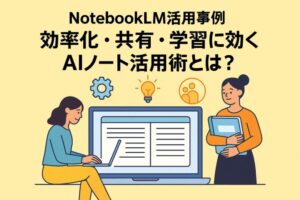はじめに
「生成AIを使って画像や文章をつくってみたい。でも、それって著作権的にだいじょうぶなの?」
生成AIが身近なツールになりつつある一方で、最近こんな疑問を持つ人がふえています。
この記事では初心者でもわかるように、生成AIと著作権の関係をやさしく解説します。
生成AIの著作権でまちがえやすい3つのポイント
この章であつかう主なポイントは、つぎのとおりです:
- AIがつくった画像や文章に著作権はあるの?
- 学習に使われたデータが著作権をおかしていることになるの?
- 「AIの出力物はじゆうに使っていい」は本当?
生成AIをめぐる著作権の問題は、まだ法律やルールがしっかり決まっていない分野です。
だからこそ、初心者がまちがって理解しやすいところもたくさんあります。
この章では、とくに「よくある思いこみ」や「トラブルをさけるための基本」をやさしくまとめていきます。
生成AIがつくった画像や文章に著作権はあるの?
生成AIが自動で作ったコンテンツには、原則的には著作権は存在しないとされています。
というのも、著作権法では「人間がつくったもの」だけが保護のたいしょうになるからです。
たとえば、画像生成AIにかんたんな指示を出して作ったものは、人間の工夫がほとんど入っていないため、著作物とは言えないとされています。
でも、もしユーザーが「どういう構図にするか」「どんな内容にするか」などをくわしく決めていて、人間のアイデアがしっかり反映されている場合は、そのぶんに著作権がつくこともあります。
ようするに、生成AIが関わっていても「どのくらい人が手を入れているか」がポイントになるということです。
学習に使われたデータが著作権をおかしていることになるの?
生成AIは、たくさんのデータを学んで新しい文章や画像をつくります。
そこで出てくる疑問が、「もし学んだデータに著作権があったら、それって勝手に使っていることにならないの?」ということです。
今の日本の法律では、「生成AIの学習に使う」目的であれば、著作物を無断で使ってもいいとされています。
だから、生成AI開発をしている会社が著作物をつかって学習させることは、基本的にはOKとされています。
でも、生成AIが出力した内容が、もとの作品にあまりにもよく似ていると、やはり問題になることがあります。
学習に使うことはOKでも、作られたものが他人の作品にそっくりだとアウトになる可能性があるということです。
「生成AIの制作物は自由に使っていい」は本当?
「生成AIが作ったものは著作権がないから、自由に使える」と思っている人も多いですが、それは正しくありません。
ほとんどの生成AIサービスには「使い方のルール(利用規約)」が決められています。
たとえば、「無料プランでは商用利用NG」「有料プランならOK」など、サービスごとにルールはバラバラです。知らずに使ってしまうと、アカウントが止められたり、法的なトラブルにつながることもあります。
出力されたものを自由に使えるかどうかは、「何で作ったか」「どういうルールで使っていいのか」をサービスごとにきちんと見てから判断しましょう。
トラブルをさけるために知っておきたい基本ルール3つ
この章であつかう主なポイントは、つぎのとおりです:
- 「商用利用OK」と書いてあっても、確認すべきこと
- 著作権者のきょかがひつようになるケースとは?
- 安心して使うためにできる、かんたんな対策
生成AIを仕事などに使うときに安心して活用するには、「これをやったら危ないかも…」というポイントをしっかり知っておくことが大切です。
この章では、初心者でもすぐできるルールや確認のしかたを紹介します。
「商用利用OK」と書いてあっても、確認すべきこと
たしかに「商用利用OK」と書いてある生成AIサービスもありますが、それだけで安心するのは危険です。
実際は、どういう使い方がOKか、どんな場面ではNGかなどが細かく決められていることが多いからです。
たとえば、「チラシには使えるけど、ロゴや販売物に使うのは禁止」など、けっこう細かいルールがある場合もあります。
使う前には、かならず公式サイトのルール(利用規約)をチェックしましょう。
わからないときは、サービス会社に問い合わせることも大切です。
著作権者の許可がひつようになるケースとは?
もし生成AIが作ったコンテンツが、他人の作品とすごくよく似ていた場合、「それはうちの著作物のマネですよね?」と言われるかもしれません。
とくに気をつけたいのは、つぎのようなケースです:
- 有名なキャラクターやロゴにそっくりな画像
- 芸能人の顔をまねたイラスト
- 実際にある作品と、構図や雰囲気がにているもの
このような場合、著作権だけじゃなく、肖像権(顔の権利)や商標権などのもんだいにもつながる恐れがあります。
とくに公開するときや商用に使うときは、注意が必要です。
安心して使うためにできる、かんたんな対策
初心者でもすぐにできる、トラブルをさけるコツは次のとおりです:
- 商用利用がOKな生成AIサービスを選ぶ
- できあがった画像や文章が他人の作品に似てないかチェックする
- 利用規約はかならず読む。不安なら問い合わせる
- 有名人やキャラクター、会社のロゴなどは使わない
この4つをおさえておくだけでも、安心して生成AIを使えるようになります。
これから変わる?著作権法と生成AIのこれから
この章であつかう主なポイントは、つぎのとおりです:
- 法律の見なおしと、気にしておきたいポイント
- ガイドラインをつくる会社や行政の事例
- 初心者でもできる「最新情報の調べかた」
生成AIの利用がふえている今、法律や社会のルールもすこしずつ変わってきています。
ここでは、今どんな動きがあるのか、そしてこれからどうやって情報をチェックすればいいかをやさしく紹介します。
法律の見なおしと、気をつけておきたいポイント
今のところ、日本では「学習OK・出力物に著作権なし」という考え方が主流のようです。
でも、海外では生成AIに作らせたものにも一定のルールを作ろうとする動きが出てきています。
たとえばEUでは、「生成AIで作ったものには『これは生成AIが作りました』とわかるようにする」などの意見が出ています。
日本でも文化庁などが報告書を出すなど、すこしずつ動きがあります。
これから法律が変わると、使い方や注意点も変わるかもしれません。
ガイドラインをつくる会社や行政の事例
大きな会社や行政の中には、すでに「生成AIを使うときのルール(ガイドライン)」を社内で作っているところもあります。
たとえば:
- 使っていい生成AIツールのリストをつくる
- 商用利用OKかどうかをあらかじめチェックする
- 生成AIで作ったものを社内で確認するフローをつくる
中小企業でも、これをまねして「うちではこう使おう」と方針をきめておくと、トラブルになりにくくなります。
初心者でもできる「最新情報の調べかた」
生成AIと著作権の話は、ルールの変化がとても早いです。
だから、「1回勉強したら終わり」ではなく、こまめにチェックすることが大切です。
簡単にできる情報チェックの方法は:
- 文化庁や総務省のホームページを見る
- 弁護士ドットコムやIT系のニュースサイトを見る
- YouTubeやSNSで、法律やITの情報を発信している人をフォローする
無理なくできることから始めて、少しずつなれていくのがコツです。
まとめ:生成AIを安心して使うためのポイント
- 生成AIが自動で作ったものには原則として著作権はない
- 学習に使うのはOKでも、出力が似ているとNGになることもある
- 使うときは生成AIサービスの「ルール(規約)」をかならず確認する
- トラブルをさけるには「似てないか?」「人の権利をおかしてないか?」を意識する
- 情報はこまめにアップデートして、変化にそなえる
免責事項
本記事は、2025年5月時点の法令や公開情報に基づいて作成されています。生成AIに関する著作権の解釈や運用は今後変更される可能性があり、すべての事例に当てはまるとは限りません。具体的な対応や判断については、専門の弁護士・法律家などにご相談ください。
当サイトでは、掲載された内容に基づく行動によって生じた損害について一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。